あなたに非認知能力はある?チェックテストで確認してみよう!!言葉にできないふわっとした能力の正体はこれだった??
非認知能力という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、IQや学力テストで計測される認知能力とは違い、「忍耐力がある」とか、「社会性がある」とか、「意欲的である」といった人間の性格的な特徴のことを指します。
偏差値がいくつだ、〇〇大学出身だなどと、学歴偏重社会だと揶揄されてきた日本ですが、近年この非認知能力がクローズアップされています。塾を経営していると、事務員や講師などを採用する場面があります。応募者が履歴書に選ぶ写真、貼り方、字の丁寧さ、書き方から、面接時刻に遅れないか、服装、靴下の色、立ち居振る舞いなどつぶさに観察するのですが、その人が醸し出す雰囲気というのはとても大切です。
塾ですので、講師を採用するときは学力も重視しますが、正直学力は後から鍛えれば、どうにでもなる部分はあるものの、人柄やコミュニケーション能力だけは、短期間に修正することは困難なものです。したがって、その人の雰囲気を非常に重視して、採用をするのですが、雰囲気っていったい何なのでしょう?
非認知能力という概念に触れ、自分が人の醸し出す雰囲気の良し悪しがここからくるのでは??と考えたため、少し調べてみることにしました。非認知能力チェックテストもつけておきましましたので、ぜひトライしてみてください。
非認知能力とは?
かつては、家庭でのいわゆる”しつけ”によって育まれてきた特質であり、誰しもある程度は備えているものと考えられてきました。特に、大家族であったり、地域のコミュニケーションが密だった昭和の時代は、親だけでなく、祖父母や兄弟、近くのおじさんやおばさんまでもが、子どもたちをしつけていた時代がありました。
しかし、近年は核家族化が進むとともに、夫婦共働きによって幼少期から保育園に預けられるケース、また一人っ子が増えたことにより、兄弟間の競争や軋轢などもなく、十分なしつけがされていないといった声も聞かれます。それを学校が代替しようとすると、いわゆるモンスターピアレントと言われる怖い親によって、妨げられ、社会人になっても最低限のマナーが身についておらず、企業が箸の上げ下ろしから研修をするなどといった話も聞こえてきます。それでは、あなたには非認知能力が備わっているでしょうか。次のチェックテストに〇×でお答えください。
非認知能力チェックテスト!!
- 一度決めたことは、何があってもやり抜く根性がある。
- 何事に対しても、意欲的、主体的に取り組むことができる。
- 一度失敗しても、諦めずに何度も挑戦することができる。
- 目の前の誘惑に惑わされず、自らを律することができる。
- 自分の置かれている状況を客観的に分析、把握することが得意である。
- 組織の中では、リーダーシップを発揮し、まとめることが得意である。
- 意に沿わないことがあってもすぐに立ち直ることができる。
- 困難に直面した場合、自分で工夫しながら局面を打開することが得意だ。
8つのチェックテストを掲げましたが、いくつ〇がついたでしょうか。
- 0から3個だったあたなは、非認知能力20% 後述の非認知能力の鍛え方を参考にしてみよう!!
- 4個から6個だったあなたは、非認知能力50% さらに鍛えて、パワーアップしよう!!
- 7個から8個だったあなたは、非認知能力100% 成功間違いなし!!しつけをしてくれた保護者に感謝ですね。
非認知能力にはどんなメリットがあるの?
このような能力を非認知能力と呼び、これがどれぐらい備わっているかによって、将来の年収、学歴や就くべき職業に大きな影響をもたらすことが明らかになっています。
今まで数多く生徒を見てきましたが、同時に我が塾で働いてくれた講師もたくさんいます。そして、学習塾でアルバイトをする学生は、学校の先生になるための教員採用試験を受験する方が多いですが、講師として採用した時点で、その人が採用試験に合格するか否かはだいたい見当がつきます。そして、その予想はほぼ100%的中してきました。しかし、この非認知能力という言葉を知るまでは、私の直感で判断しており、根拠はと聞かれると非常に曖昧だったのですが、その講師の塾での生徒への接し方、教え方、同僚講師との関係、塾長である私への接し方をこの8項目から検討すると、採用試験に合格していく講師は、ことごとくこれらの資質を兼ね備えていることを感じたのです。
ある問題を自分が解けることと、それを教えられることはまったく別の能力です。講師がどれだけ解けても、生徒が解けるようにならなければ、何の意味もありません。いかに生徒が解けるようにさせるかは、簡単なようでいて意外と難しいものです。偏差値の高い高校を出て、偏差値の高い大学に在籍しているからといって、この能力が高いとは限りません。まず、生徒の状況を分析すること。どこでその生徒がつまづいているかが、的確に把握できることが最初になります。ここがズレてしまっては、どんな解説をしようとも、生徒には届きませんので。
次に、つまづいているポイントがわかったら、細かく細分化し、生徒がどこでつまづいているかを理解させることが必要になります。そして、そのポイントにつき、図を描いたり具体例などを示しながら、解決の糸口を生徒にイメージさせることが必要になってきます。
こういうことは、研修で伝えても、すぐに要領を押さえられる講師と、そうでない講師にわかれてしまいます。結局はこちらの言わんとしていることを理解して、咀嚼する能力に他ならないのですが、この能力に長けているなと思える講師は、一様に教員採用試験に一発で合格していきます。逆にそこに難がある講師は、2回、3回と挑戦することになっていました。
以上のことから、自分自身も含めて、この非認知能力を習得することは、極めて重要なことなのではないかと思うのです。
非認知の力の中で、最も重要といわれる自己肯定感については、あなたに自己肯定感はある? 非認知能力を育む方法とは??の記事もあわせてどうぞ。
非認知能力の鍛え方
非認知能力が重要だとしても、これをどのように獲得するのか、また今からでも鍛えることができるのか否か、これこそが最大の関心事になってきます。
前述の8つのチェックテストの中でも、1のやり抜く力と4の自制心が非認知能力の中でも特に重要なものとされていますが、一度決めたことをやり抜くことは、大人でも非常に困難を伴います。毎日3キロウォーキングをするとか、毎日ジムへ行くなど、色々と決めてもみますが、なかなかやり抜くことは難しいものです。
塾の生徒にも、毎日決まった時間に決まった範囲の宿題をしないさいという課題を出しますが、できない生徒も現に存在します。ただ、中にはそれをきちんと守って実行してくる生徒がいます。4の自制心にもつながりますが、何のために宿題をするのか、それは成績をあげるためだから、塾で出された宿題を毎日決まった量行わなければならない!!とルーティン化できる生徒は強いです。そこには、確固たる目的、信念があるからこそなせる業です。
これが小さいころからのしつけとして、習慣化している子どもは、当たり前のようにこれをやり遂げます。だからこそ、学習習慣もつき、結果として成績もUPしてきます。ただ、この習慣がない場合は、これを何とかしてつけていく必要があります。
結果にコミットするでお馴染みのライザップはここにクローズアップしています。どんなトレーニングをしたかというよりも、毎日の食事をしっかりと管理すること。どんなに運動をしても、寝る前にラーメンを食べたら、瘦せるものも痩せません。
勉強では、授業をしない塾と銘打って、武田塾という学習管理型の塾が有名です。塾がすることは、いつどの教材を使って何をどこまで、勉強するのか、その計画立てと実行の有無を確認してくれることです。問題の成否はどうぞご自分でというスタイルです。しかし、こここそが、自制心をもって、自らやり抜く力の有無が試されるわけですが、今は非認知能力の部分も外注する時代になってきているようです。
しかし、先ほども述べた通り、非認知能力は鍛えられます。はじめはライザップや武田塾に管理をお願いしていても、徐々にペースがつかめれば、自分でもそれを習慣化することはできるようになってくるはずです。自分なりの計画を立ててみて、なかなかそれが守れないといった場合には、今の時代オンラインで様々なスケジュール管理をしてくれるサービスもあるようですので、そのようなものを使いながら、非認知能力を鍛えていくのも手かもしれませんね。
我が娘とは、毎日一緒にやろうねと決めた勉強も親の都合で習慣化できないことがないよう、さっそく明日からも続けていきます!!
関連記事:非認知の力の中で、最も重要といわれる自己肯定感については、あなたに自己肯定感はある? 非認知能力を育む方法とは??の記事もあわせてどうぞ。





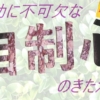

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません